皆さん、こんにちは。
りょう先生です。
今日は歴史総合の2回目。ヨーロッパに主権国家が成立する時代の話です。
突然ですが「主権国家」って、なんだかわかりますか?
「主権」とは、「その国のことを全て決める権利」のこと。
中世までの時代、国王は必ずしもその国の中で自由ではなかった。
国外であればキリスト教の伝統に従わなければいけなかったし、国内であれば諸侯(貴族)達の言うことも完全に無視することはできなかった。
それが近代になると「主権国家」という考え方が生まれて、「主権」を持った国王の権力は絶対、そして「主権」を持った国民の権力は絶対、となっていくんだ。
いわゆる「民主主義」国が生まれるための準備段階になったわけ。
どのような経緯でヨーロッパの主権国家体制が形成されたのか、見ていこう。
近代的な主権国家の成立
16〜17世紀、ヨーロッパでは、それまで強大な力を持っていた神聖ローマ帝国が弱体化しつつありました。
まさに、アジアで、オスマン帝国、ムガル帝国、明や清が栄えていた頃です。
中世の頃、神聖ローマ帝国の皇帝は、スペインなどの君主も兼ねており、強い影響力を持っていました。
さらに国家を超えてキリスト教という形で強い影響力を与えていたのがローマ教皇です。
ところが、フランスやイギリス、オランダなどの周辺諸国の君主(国王)が政治権権力を握り、中央集権化を進めていきました。
国王は国内で諸侯(貴族)を抑え、絶対的な権威を持つ王として支配するようになりました。
そして、それらの国々は対等な立場で外交関係を築くように。
1648年にはウェストファリア条約が結ばれ、ドイツと周辺国が講和を結び(戦争をやめ)、オランダやスイスの独立も認められました。
このように、互いの国々がそれぞれ主権をもつ国際秩序のことを主権国家体制と言います。
ただし、この時、主権はまだ君主(国王)にあった。
この主権を、のちに民衆が手に入れるようになっていく。
イギリスで始まった立憲君主政
イギリスは16世紀後半、エリザベス1世の時に絶対王政の最盛期を迎えました。
女王の権力が最大となり、最も栄えた、ということだね。
その後、地主を中心とする議会が力をつけていき、1642年にはクロムウェルが中心となって、一時的に君主政を排除。
これをピューリタン革命という。
ピューリタンとは「清教徒」という意味で、クロムウェルらが信じていたキリスト教プロテスタントの中の一つのグループのこと。
このあと一時期、君主政にもどるものの、議会は1688〜89年に名誉革命を起こします。
革命というのは暴力がつきものだった。しかし、血を流さずに起こした革命だから「名誉」革命、ということですね。
そして議会は権利の章典を定めた。
国王が議会の同意もなく、勝手に法律を作ったり、税金をかけたりするのは違法で、議会の権利をちゃんと認めなさい!という内容だね。
このように法の支配を原則として議会が政治の中心を担う世界初の立憲君主政がスタート。
しかし、この時期はまだ選挙に出られる人も、投票できる人もごく一部の特権階級だけだったのは注意。
それでも、やがて議会の多数派政党が政権を握る議院内閣制が確立し、日本を含む近代国家の政治モデルとなっていったのです。
ヨーロッパ諸国の動向
ここからはヨーロッパ諸国、それぞれの動向を見ていきましょう。
フランス
ヴェルサイユ宮殿に象徴されるように、ルイ14世の頃、フランスは絶対王政の絶頂期にありました。
るい14世は議会を開くこともなく、思いのままに国政を動かし続けました。
その結果、富はブルボン王朝に集中し、フランスはヨーロッパ文化の中心となりました。
フランスの民主化は18世紀後半のフランス革命を待たねばなりません。
ドイツ
10世紀以降、強大な神聖ローマ帝国が支配していた地域でした。
しかし、16世紀の宗教改革などによって皇帝は弱体化。
その結果、政国内の多数の諸侯(貴族)たちが力をつけることに。
17世紀の三十年戦争のあとは、諸侯が収める領邦国家のなかからプロイセンが台頭し始めました。
ちなみに30年戦争は、ドイツ(神聖ローマ帝国)の内戦に始まり、国内の宗教対立をきっかけに、フランスなどの周辺諸国を巻き込み戦争に発展。
この戦争の講和条約が上記のウェストファリア条約でした。
イタリア
イタリアはヴェネツィア、ジェノヴァなどの自治都市(都市国家)が成立していました。
古代ローマ帝国に起源をもつ共和政を採用し、地中海貿易や東方との交易で力をつけた富豪の貴族たちが中心になって国を治めました。
宗教改革
主権国家体制が確立されていくなか、キリスト教にも大きな変革の時代を迎えます。
ローマ教皇を頂点とするカトリックの教えに対し、16世紀前半、ドイツのルターとスイスのカルヴァンから強い疑問の声が上がりました。
カトリック教会が大聖堂新築の資金集めのために贖宥状(免罪符)を発行。
人々が神に救われるためには神に通じた聖職者たち、カトリック教会を通じてでなければならない。
ルターやカルヴァンはカトリックに対して強く抗議(プロテスト)しました。
「真の信仰は聖書にある」と主張。
当時、グーテンベルクによる聖書の活版印刷が広がり、一般のキリスト教徒も聖書を読めるような状況が整いつつありました。
そんな聖書の中には「カトリック教会を大事にするべき」なんてことは一言も書いていない。
こうして、のちにプロテスタントと呼ばれる改革者たちが始めた宗教改革の動きが、ローマ教皇の支配からの解放に結びつきました。
さらにこれは主権国家の形成を進めることにもなったのです。
カトリック教会の中でもこの動きに危機感を感じ、内部改革を進めたひとびとがいました。
スペインではイグナティウス=ロヨラによってイエズス会が結成され、フランシスコ=ザビエルはキリスト教を布教するため来日しましたね。
科学革命
17世紀、ヨーロッパでは自然科学も大きく発展しました。
旧来のカトリック教会を中心とした宗教のみを信じる、というメンタリティから解き放たれて、合理的な考え方が支持されていきました。
イタリアの天文学者ガリレイ(ガリレオ=ガリレイ)はコペルニクスのとなていた地動説を科学的に証明。
イギリスの科学者ニュートンは万有引力の法則を発見。
この頃ヨーロッパ各国で科学協会やアカデミーが創設され、科学者の活動の場が広がっていきました。
「科学こそが人間を幸福にしてくれる」という考え方も起こっていったのです。
こうした一連の動きは科学革命とよばれます。
しかし、科学的な真理の探究は、「神が世界を創生した」という宗教の教義の否定にもつながるため、キリスト教会からの猛反発を受けました。

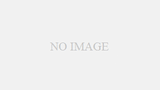
コメント